大会長挨拶
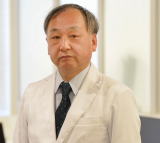
日本臨床倫理学会第13回年次大会 大会長
野口 善令(豊田地域医療センター 総合診療科 学術教育顧問)
日本臨床倫理学会第13回年次大会を、2026年3月21日(土)と22日(日)を会期として開催させていただくことになりました。年次大会のテーマは「問い、対話し、進化する臨床倫理」です。これまで第11回大会では臨床倫理が「医療・ケアの基盤」として確立されたことを確認し、第12回大会では実践者の視点から人材育成と地域展開の課題を明確にしてまいりました。第13回大会では、その基盤の上に立ち、臨床倫理が絶えず問いを発し、多様な立場の人々との対話を通じて進化し続ける学問分野であることを強調したいと考えています。
学会設立から13年を経た今、私たちが直面している最重要課題の一つは、倫理コンサルテーションにおける倫理的検討の質の向上です。全国の医療機関において倫理コンサルテーションの体制は整備されてまいりましたが、その内容や手法には大きなばらつきがあることも事実です。単に形式的な検討に終わることなく、真に患者・家族の価値観に寄り添い、医療チームの倫理的感性を高める質の高いコンサルテーションを実現するためには、継続的な研鑽と手法の洗練が不可欠です。
また、地域での倫理活動展開は急務となっています。高齢化の進展とともに、医療・ケアの場は病院から在宅、介護施設、地域包括ケアシステム全体へと拡がっています。地域ネットワークの構築、医療・介護連携における倫理的課題への対応、そして地域住民を含めた倫理的対話の場の創出が求められています。各地域の特性を活かしながら、どのように持続可能な倫理活動を展開していくか、具体的な方策を共有したいと考えています。
さらに、急速に発展する医療技術や思想は私たちに新たな倫理的問題を提起しています。認知症に関する科学技術の発展と臨床倫理、ナッジ(リバタリアンパターナリズム)—選択の自由を保持しながらも、よりよい選択へと人々を誘導する手法—や多様な価値観や文化的背景を持つ患者・家族への対応における倫理的相対主義と意思決定支援など、これらの新しい課題に対して、臨床倫理学がどのように応答し、実践的な指針を提供できるのか、学際的な対話を通じて探究していく必要があります。
一方で、継続的課題への取り組みも怠ることはできません。終末期医療や移植医療における意思決定支援、医療者の職業倫理とその労働環境の安全性の関係など、臨床倫理学が一貫して取り組んできた根本的な課題は、社会情勢の変化とともに新たな様相を呈しています。これらの課題に対して、蓄積された知見をもとに、より深い理解と実効性のある対応策を見出していくことが重要です。
第13回年次大会では、これらの四つの方向性を軸に、参加される皆様が互いに問いを共有し、多様な立場からの対話を重ね、臨床倫理の新たな地平を切り拓く場となることを目指しています。理論と実践、個別事例と制度的課題、病院と地域、現在の課題と未来への展望、これらすべてを繋ぐ学びの場として、年次大会を位置づけたいと考えています。
臨床倫理は決して完成された学問ではありません。常に現場からの問いに応答し、時代の変化に対応して進化し続ける動的な営みです。第13回年次大会が、その進化の一歩となり、参加された皆様が各々のフィールドで新たな実践を始めるきっかけとなることを心から願っています。多くの皆様のご参加をお待ちしております。